ビリルビンを完全マスターしましょう!
今回はビリルビンについて、やっていきたいと思います!
ビリルビンについて
暗記だけでこれを覚えてしまうのはもったいないです
ビリルビンは、その仕組を理解すれば
必ず論理的に解ける問題が多いです!
国試かけこみ寺では、
- 単純にひたすら暗記すべき知識
- 理解して、論理的に解くべき知識
この2つの知識を、できるだけ同じくらいの割合で
身につけることを推奨しています
そして、ひたすら暗記すべき知識は
国試勉強、終盤戦に行うことをオススメします
具体的には年が明けてからですね
年が明ける前までは、なるべく理論的に解くための
長期的な知識を育てる時間に当てたほうが
あとあと、効率的ではないかと考えます!
この記事では
チェックポイント
ビリルビンの代謝系
直接ビリルビンと間接ビリルビンの違い
黄疸の種類・覚え方
について、理解して問題を解けるように
わかりやすく解説していきたいと思います!
それではいってみましょう!!
ビリルビンとはヘモグロビンの代謝物である
そもそもビリルビンとは
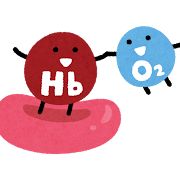
古い赤血球が壊れた時の
ヘモグロビンが代謝されたものです
ちなみに古い赤血球を壊しているのは
脾臓 という臓器です
脾臓で
ヘモグロビンがビリルビンに変換されると
次に肝臓で処理されます
しかし
ヘモグロビンから代謝直後のビリルビンは
水にほとんど溶けません!(重要)
そのため、アルブミンというタンパク質に結合して
血液中を運ばれ肝臓にいきます

直接ビリルビンと間接ビリルビン
アルブミンとの結合を解除し
ビリルビンは肝臓へやってきました

ここでビリルビンは
グルクロン酸抱合
という処理を受けます
ビリルビンはグルクロン酸抱合を受けると
水に直接溶けることができます
すなわち
肝臓でグルクロン酸抱合を受けたビリルビンを
直接ビリルビン=抱合型ビリルビン
といいます
(厳密には直接の由来は水に溶けるという意味ではありませんが、覚えやすいのでこのように説明しています)
直接ビリルビンに対して
肝臓で抱合する前の
水に溶けにくいビリルビンを
間接ビリルビン=非抱合型ビリルビン
といいます
この違いさえ覚えておけば
直接ビリルビンと間接ビリルビンの説明は完璧です!
その後の代謝ですが
水に溶けるようになった直接ビリルビンは
胆汁の材料となり 十二指腸に分泌されます
↓胆汁の役割についてはこちらの記事をどうぞ
消化の補助として役割を終えた胆汁は
小腸で腸内細菌によって分解・再吸収されます
このとき!
ビリルビンはウロビリノーゲンという物質になります
ウロビリノーゲンは再吸収され
肝臓に戻り、また胆汁の材料として使われるのです
これを胆汁の腸肝循環といいます
また、一部のウロビリノーゲンは
尿中に排泄されます
これがヘモグロビン→ビリルビン→ウロビリノーゲン
という代謝の一連の流れになります
まとめると
間接ビリルビン=非抱合ビリルビン
- 肝臓でグルクロン酸抱合を受ける前のビリルビン
- 水に溶けにくいので、アルブミンと結合して血中に存在する
直接ビリルビン=抱合型ビリルビン
- 肝臓でグルクロン酸抱合を受けた後のビリルビン
- 水に直接溶けることができる
- 胆汁の材料となる
- 腸内細菌によって、ウロビリノーゲンになる
ウロビリノーゲン
- 腸で再吸収され肝臓で再利用(腸肝循環)
- 一部は尿中に排泄される
3種の黄疸の見分け方
ビリルビンが関わる重要な症状として
黄疸があります
黄疸とは血中のビリルビンが過剰になること
皮膚などにビリルビンが沈着し
黄色くなってしまう症状のことです
特に、白目のような部分は黄色の変化が強いです
黄疸の原因は
病気の影響でビリルビンが増加してしまうこと
黄疸には以下の3種類があります
- 溶血性黄疸(=肝前性)
- 肝細胞性黄疸(=肝性)
- 閉塞性黄疸(=肝後性)
これらの黄疸を見分けるために重要なのが
直接ビリルビンと間接ビリルビン
どちらが上昇しているのか、という問題です
これを見分けることはそう難しくはありません
肝臓の前に原因があれば
グルクロン酸抱合を受けていないので
間接ビリルビンが過剰
肝臓の後に原因があれば
グルクロン酸抱合を受けた後なので
直接ビリルビンが過剰
この基本ルールを覚えておけば
対応可能です
溶血性黄疸=肝前性
赤血球の溶血が起こるとヘモグロビンが大量に流出し
結果的にビリルビンの量が多量に増えます
しかし、肝臓では多量のビリルビンを抱合しきれません
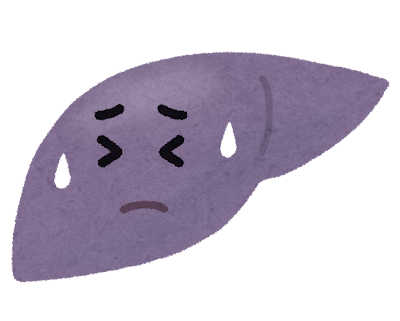
その結果、溶血性黄疸では
抱合前の、間接ビリルビンが過剰になってしまいます
溶血性黄疸の代表疾患として
- 溶血性貧血
- マラリア(赤血球に虫が寄生し壊れやすい)
- 新生児黄疸
などがあります
新生児黄疸は、生まれたばかりの赤ちゃんに起きる黄疸で
新生児では赤血球の代謝が激しく、黄疸になりやすいことがあります
新生児黄疸は基本的には生理的なものであることが多いです
肝細胞性黄疸=肝性
肝細胞性黄疸は間接・直接どちらのパターンもありえます
グルクロン酸抱合時に問題がある場合
間接ビリルビンが上昇します
抱合した後の胆汁の生成に問題がある場合
直接ビリルビンが上昇します
肝性の場合は、どの機能に問題があるかで変わってきますが
グルクロン酸抱合を受けているかいないか、が見分けのポイントです
代表疾患は
- 急性肝炎
- 肝硬変
- 肝癌など
肝機能の低下によるものがあります
閉塞性黄疸=肝後性
閉塞性黄疸とは
胆汁の通り道が塞がることに原因があります
胆汁に含まれるのは
グルクロン酸抱合を受けた後のビリルビンですから
直接ビリルビンが上昇します
そして代表疾患は
- 胆管結石
- 膵頭部癌など
胆汁の通り道にできる石や癌になります
さて、それでは実際の問題について
やっていきたいと思います!
ビリルビンに関する症候群
臨床検査技師・薬剤師を目指す方は必ず覚えておきましょう!
ビリルビンに関する症候群です
直接ビリルビン上昇:Dubin-Johnson症候群とRotor症候群
直接=DiRect と覚えましょう!
間接ビリルビン上昇:Gilbert症候群とCrigler-Najjar症候群
直接ビリルビンの疾患名を覚えてしまえばOKです!
直接型ビリルビンが増加するのはどれか【PT】
- 新生児の生理的黄疸
- 遺伝性球状赤血球症
- 先天性胆道閉塞症
- 自己免疫性溶血性黄疸
- Rh血液型の不適合
間接ビリルビンの上昇は溶血性
これを覚えておくだけでも
問題がかなり解きやすくなります
1.新生児の生理的黄疸
新生児は赤血球の数が多く溶血しやすいので間接↑
2.遺伝性球状赤血球症
遺伝で赤血球の形が異常になり溶血しやすい ので間接↑
3.先天性胆道閉塞症
胆道が閉塞している、胆汁の分泌に問題あり
グルクロン酸抱合は行われているので
直接ビリルビンが上昇
正解は3番
4.自己免疫性溶血性黄疸
溶血が起きるので間接↑
5.Rh血液型の不適合
血液型不適合では溶血が起きるので間接↑
もう一度言いますが
間接ビリルビンの上昇は溶血性
これだけはしっかり押さえておきましょう
ビリルビンについて、正しい組み合わせはどれか【Ns】
<黄疸の原因> ─ <増加するビリルビンの種類> ─ <疾病>
- ビリルビンの過剰生成─ 直接ビリルビン ─ 新生児黄疸
- ビリルビンの抱合異常 ─間接ビリルビン ─ 溶血性黄疸
- 肝外胆管の閉塞 ─ 間接ビリルビン ─胆管癌
- 肝内胆管の障害 ─ 直接ビリルビン ─原発性胆汁性肝硬変
<黄疸の原因> ─ <増加するビリルビンの種類> ─ <疾病>
1.ビリルビンの過剰生成─ 直接間接ビリルビン ─ 新生児黄疸
新生児黄疸は溶血性=間接上昇
出てくる頻度は非常に高いです
2.ビリルビンの抱合異常 ─間接ビリルビン ─ 溶血性黄疸
溶血性黄疸=間接ビリルビン上昇
ここまではいいですが、抱合異常ではなく
溶血による過剰生成が原因です
3.肝外胆管の閉塞 ─ 間接直接ビリルビン ─胆管癌
胆管癌は閉塞性黄疸ですね
肝臓でのグルクロン酸抱合は終わっているので
直接ビリルビンの上昇
4.肝内胆管の障害 ─ 直接ビリルビン ─原発性胆汁性肝硬変
正解は残りの4番となります
肝内胆管の障害というのは肝臓の胆汁分泌の障害
分類としては肝性黄疸です
胆汁の生成は終わっているので、
グルクロン酸抱合後の直接ビリルビンが上昇してきます
ちなみに 原発性胆汁性肝硬変 は自己免疫疾患です
HPLC法によるビリルビンの分類(臨床検査技師に必要な知識)
HPLC法では溶出が早い方から δ→γ→β→α となり、水に溶けやすいものから溶出されます
δ-ビリルビン:ビリルビンが体内に長期滞留すると、アルブミンと結合します。これがδビリルビンで、通常の測定では直接ビリルビンとして測定されます。
γ・β:γはグルクロン酸が2分子結合、βは1分子結合した、直接ビリルビンです
α:最も溶出が遅いαが間接ビリルビンです
まとめ
- 非抱合型ビリルビン=間接ビリルビン=不溶性
- 抱合型ビリルビン=直接ビリルビン=水溶性
- 溶血性黄疸は間接ビリルビン上昇
- 閉塞性黄疸は直接ビリルビン上昇
この記事を数回読み直せば
ビリルビンについては理解して
問題を解くことができるようになると思います!
それではまた!
臨床検査技師国家試験のビリルビン関連問題はこちらからどうぞ!
MT66-AM37:グルクロン酸抱合の不良により間接ビリルビンが増加するのはどれか。
MT64-PM38 血清ビリルビンについて正しいのはどれか。


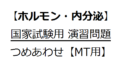

コメント
3種類の横断の見分け方の溶血性黄疸の最後の説明が”抱合前の直接ビリルビンが過剰になってしまう”となっていましたが、関節ビリルビンが過剰になるの間違いでしょうか?
ご指摘ありがとうございます!
仰る通りです。抱合前は間接ビリルビンです。
記事内容を修正いたしました。
とてもわかりやすかったです。ところで、直接ビリルビンが低値の場合、病的意義はあるのでしょうか。
ありがとうございます!健常者では間接ビリルビンが優位で、直接ビリルビンは低値であることが多いです。直接ビリルビンが血中に漏れるということ自体が健常者ではほとんどないので、病的意義はないと考えられます。