平成31年2月20日(水)に実施された
第65回臨床検査技師国家試験問題について
一部の分野をわかりやすく解説しています!
問題(+別冊)と解答は厚生労働省のHPで公開されています
※以下の問題の出典は全て、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp190415-07.html)で公開している問題を引用しています。
問題に対する解説は国試かけこみ寺のオリジナルとなります。
MT65-PM35 分光光度法において共存物質の影響試験の対象となるのはどれか。2つ選べ。
1.過酸化水素
2.ヘモグロビン
3.アスコルビン酸
4.アスパラギン酸
5.ペルオキシダーゼ
分光光度法における共存物質の影響試験の対象 とは
吸光度に影響を与える物質
を指します
具体的には、
・吸収波長に直接影響を与える=色がついている
・酸化還元反応を阻害する
の2つを考えれば良いでしょう
・吸収波長に直接影響を与える=色がついている
これに該当するのは、
- ヘモグロビン(溶血)
- ビリルビン
- 乳び(脂質)
などがあります
・酸化還元反応を阻害する
これに該当するのは特に
- アスコルビン酸(還元物質=抗酸化作用)
- 次亜塩素酸・さらし粉(酸化物質)
などがあります
特に、ペルオキシダーゼ(POD)を用いる測定系では
PODが過酸化物質(H2O2)を分解することで生じる酸化反応を検出します
この場合、アスコルビン酸では偽陰性
さらし粉では偽陽性反応が起きることになります
ということでここの答えは
2.ヘモグロビン
3.アスコルビン酸
となります
MT65-PM36 尿酸の酵素法試薬に含まれているのはどれか。2つ選べ。
1.ウリカーゼ
2.ウレアーゼ
3.キサンチン
4.アラントイン
5.ペルオキシダーゼ
尿酸・酵素 といえばまずはウリカーゼです
ウリカーゼの別名は尿酸オキシダーゼ(尿酸を酸化する酵素)ともいいます
・ウリカーゼの反応系(重要なのは太字部分です)
尿酸+O2 (+H2O) →アラントイン+H2O2 (過酸化水素)+CO2
尿酸の測定は、次に、ウリカーゼ反応で発生した
過酸化水素をペルオキシダーゼで分解し
発生した酸素によって色原体が酸化され色が変化します
この変化を吸光度でとらえることとなります
以上のことから答えは1,5となります
MT65-PM37 日本臨床化学会JSCC勧告法で吸光度の減少から活性値を求めるのはどれか。2つ選べ。
1.CK
2.LD
3.AST
4.アミラーゼ
5.コリンエステラーゼ
JSCC法での酵素の吸光度測定については
酵素反応によって生成もしくは消費された
NADH:340 nm の波長測定 がカギとなります
・NADHが消費される反応=吸光度の減少
AST, ALT, ChE(コリンエステラーゼ)
このことから答えは3,5ですね
・NADHが生成される反応=吸光度の増加
LD, CK
4.アミラーゼは、反応によってできるニトロフェノール系の増加を測定するため、吸光度も増加します。他にはALP(アルカリホスファターゼ)も同様の測定系になります
↓以下の記事で更に詳しく解説しています!
MT65-PM38 水溶性ビタミンはどれか。
1.カルシフェロール
2.トコフェロール
3.メナキノン
4.リボフラビン
5.レチノール
水溶性ビタミンはV.B群とV.Cになります
ちなみに、脂溶性ビタミンの覚え方は、脂肪DAKE(だけ)です
この問題のように、ビタミンの化学物質名が出てくることもあるため
名前は覚えなくてはいけませんね
1.カルシフェロール:V.D
2.トコフェロール:V.E
3.メナキノン:V.K
4.リボフラビン:V.B2
5.レチノール:V.A
答えは4となります
↓ 以下の記事でも詳しく解説しています!
MT65-PM39 骨格筋でアンモニアが結合して生成するのはどれか。
1.アルギニン
2.オルニチン
3.グルタミン
4.シトルリン
5.カルバモイルリン酸
アンモニアは主にタンパク質を代謝で発生しますが
有毒であるため、体内で様々な処理がされています
国家試験で最も頻度の高いものは、
肝臓で行われる尿素回路(オルニチン回路)ですね
1,2,4,5は尿素回路に登場する物質です
そして、もう一つが骨格筋での処理です
骨格筋の代謝によって生成されるのはグルタミン酸です
このグルタミン酸がアンモニアと結合し、
グルタミンとなって、アンモニアを処理できるようになります!
よって、答えは3になります
臨床化学もなかなか重い問題が多いですが
しっかり整理して、理解、説明をできることが重要となります!
ではまた次回!
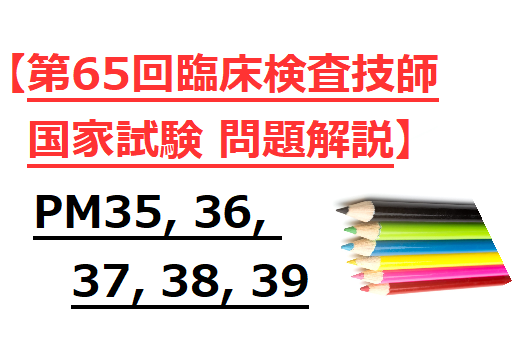
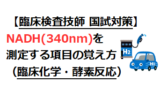
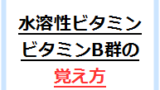
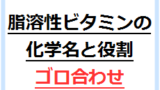
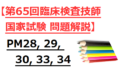
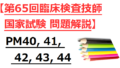
コメント