国試かけこみ寺です!
今回は臨床検査技師国家試験の医用工学分野のかけこみ記事です
医用工学分野は人によってはほとんど勉強していない人もおおいかもしれません
といっても、200点中の12点は占める部分ですから、決して小さくはないですよね
そこで今回は、医用工学の中でも
・比較的解きやすい(付け焼き刃でなんとかなる)
「2進数」および「マクロショック・ミクロショック」
について、最低限覚えておくべき過去問をしっかり見ていきましょう!
※必ず出るという保証はありませんのでその点はご了承ください
この記事が
- 医用工学にあまり手をつけていない
- 文系からきているので計算を避けてきた
という人に1点でもプラスできるチャンスになれば幸いです!
この記事を読みながら約10分程度で勉強ができる構成になっています
2進数の問題
基礎知識として
2進数は0と1だけで数字を表す方法です
0=0、1=1
10=1×21+0×20=2
11=1×21+1×20=3
※0乗は1になります
100=1×22+0×21+0×20
=4+0+0=4
101=1×22+0×21+1×20
=4+0+1=5
といった具合です
2の0乗、2の1乗、2の2乗、2の3乗…
に対して、1か0をかけて、足し算をすれば
普段使っている10進数になります
必然的に下1桁が
- 0なら偶数
- 1なら奇数
となります
MT61-PM98 二進法で110から11を引いた値はどれか。
- 1
- 10
- 11
- 100
- 101
2進数の足し算や引き算は2進数の状態でそれなりのやり方がありますが
おすすめは、10進数に戻して計算してしまう方法です
110=4+2+0=6
11=2+1=3
6-3=3です
3をもう一度、2進数に戻すと11なので、答えは3番です
MT52-AM85 二進法で11と11を加えた値はどれか
- 100
- 110
- 111
- 1000
- 1111
11=1×21+1×20=3
ですから、3+3=6で
6を2進数に戻すと
1×4+1×2+0×1なので、答えは2.110になります
情報系の問題
10年以上前の過去問ですがよく出ていたものとして
ビット(bit)とバイト(byte)の問題があります
ビットとバイトは情報量の単位です
1ビットは2の1乗の情報
2ビットは2の2乗
1バイト=8ビット=2の8乗
2バイト=16ビット=2の16乗
というのが基本になります
MT57-AM98 2バイトで表すことができる情報の個数として正しいのはどれか。
- 24
- 28
- 216
- 232
- 264
2バイト=16ビット=2の16乗で答えは3
MT56-AM98 情報をコード化するとき、10ビットで表現できるコードの種類はどれか。
- 64
- 128
- 512
- 1024
- 4096
10ビット=2の10乗=1024が答えになります
指を折って2を掛けていったり、紙に書いて地道に計算しましょう
MT52-AM87 3原色を組合せて画素の表示を行うディスプレイで,それぞれの色が4ビットの階調で表されるとき,画素の表現できる色の数はどれか。
- 12
- 64
- 256
- 1024
- 4096
3原色の色が4ビット=24の色調があるということでその組み合わせは
24×24×24=212
ということで答えは4096です
これも計算が苦手でも貪欲に紙に書くなどして計算すれば答えは出ます
MT51-AM82 2バイトで表すことができる情報の個数として正しいのはどれか。
- 16
- 256
- 1024
- 4096
- 65536
先程のMT57-AM98の問題とほぼ同じです、2の16乗を地道に計算する必要はなく、2の12乗が4096ですからそれより大きくなるとわかればOKです
ちょっと古い問題が多かったですが、こういった2の○乗、2進数絡みの問題は非常に点がとりやすいですから、仕組みだけでも覚えておきましょう
以下は最近の問題
MT65-PM97 DNAの塩基をA、C、G、Tの4種類で表すとき、 連続した塩基3個の配列で表現できる最大の情報量はどれか。
- 12
- 24
- 32
- 64
- 81
塩基3個の配列があり、塩基は4種類ですから
4×4×4=64が答えになります
もし、この情報量は何ビットか?
と聞かれた場合には、64=2の6乗ですから、6ビットになりますね
マクロショックとミクロショック
ピンポイントな知識ですが、出ている頻度は比較的高めです
覚えることはシンプルです
- マクロショック:体表に流れる電流
- ミクロショック:心臓に流れる電流
医用工学機器を扱うにあたって、これ以上流れたらヤバイよね、という電流の大きさの基準がこの2つです
マクロショックで覚えることは3つ
- 最小感知電流:1mA
- 離脱電流 :10mA
- 心室細動 :100mA 以上
・最小感知電流とは体表に流れて感知できる電流の大きさです
・離脱電流とは10mAくらいの電流であれば、自力で抜け出せるということです
10~20mAを大きく越えると、電流のしびれによって自力で抜け出せないということになります
・100mAを超えると心室細動が発生し非常に危険な状態となります
ミクロショックは0.1mAで心室細動 これだけを覚えましょう
心臓に0.1mA(100 μA)の電流が流れてしまうと、非常に危険な状態ということです
具体的には、心臓カテーテルや体外式ペースメーカーなどからの感電ということになります
以上を踏まえて問題を見ましょう
MT65-AM98 体表から商用交流100Vが加わって生じる電撃で、心室細動を発生させる電流閾値はどれか。
- 100 μA
- 1 mA
- 10 mA
- 100 mA
- 1 A
体表・心室細動 マクロショックのことで、心室細動の危険は
100 mAが答えになります
MT62-AM97 商用交流によるマクロショックで最小感知電流(mA)はどれか。
- 0.01
- 0.1
- 1
- 10
- 100
マクロショックの最小感知電流は 1mAが答えになります
MT59-PM97 人体の電撃反応(商用交流・1秒間通電)でマクロショック(心室細動)が生じる電流値[mA]の大きさはどれか。
- 0.01
- 0.1
- 1.0
- 10
- 100
心室細動・マクロショック 答えは100mAです
MT56-AM97 商用交流電流(50 Hz)を皮膚から1秒間通電したとき、人体の電撃反応における離説電流値はどれか。
- 0.1mA
- 1mA
- 10mA
- 100mA
- 1000mA
離脱電流ということで、10mAです
最後に、66回で出た応用問題です
MT66-PM96 100kHzの交流電流が体表の2か所に張り付けた電極間に流れたとき、およその最小感知電流と考えられるのはどれか。
- 10μA
- 100μA
- 1mA
- 100mA
- 1A
最小感知電流といえば、1mAでしたが、この問題は100kHzという前提があります
一番初めに書いた、マクロショックとミクロショックは低周波(1kHz以下)を前提とした話になり、1kHzを越えると、周波数に比例して電流を感じにくくなります
すなわち、100kHzでは100倍感じにくくなるので、最小感知電流は100倍の100mAが答えになります
まとめ
- 2進数の足し算・引き算は10進数に戻して、答えをまた2進数に戻すとやりやすい
- 1ビットは2の1乗の情報
- 2ビットは2の2乗
- 1バイト=8ビット=2の8乗
- 2バイト=16ビット=2の16乗
マクロショックは体表から流れる電流
- 最小感知電流:1mA
- 離脱電流 :10mA
- 心室細動 :100mA 以上
ミクロショックは0.1mAで心室細動
以上、かけこみ(付け焼き刃)でなんとかなりそうな医用工学の知識の紹介でした!
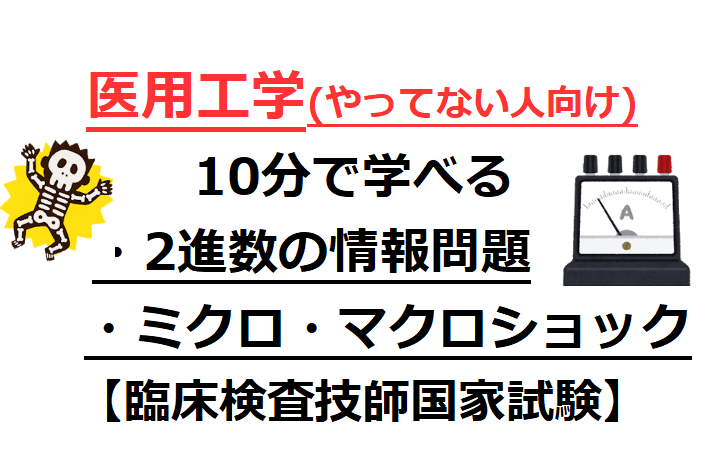
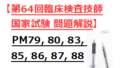

コメント
国試直前にこの記事を見つけて、医用工学に自信をつけて本番を迎えられました。
そしてなんと、ちょうどこの記事のおかげでわかるようになったところが国試で出てきて解けました!
すごく嬉しかったです!ありがとうございました!
大変嬉しいお言葉ありがとうございます!直前にちゃんと記事を読み込んだことが素晴らしいです