医療系国家試験の解説サイト
国試かけこみ寺です!
令和7年2月19日(水)に実施された
第71回臨床検査技師国家試験問題について
一部の分野をわかりやすく解説しています!
問題(+別冊)と解答は厚生労働省のHPで公開されています
※以下の問題の出典は全て、厚生労働省のホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-07.html)
で公開している問題を引用しています。
問題に対する解説は国試かけこみ寺のオリジナルとなります。
- MT71-AM29 無機質の動態で誤っているのはどれか。
- MT71-AM30 蛋白で誤っているのはどれか。
- MT71-AM31 ホルモンで正しいのはどれか。
- MT71-AM32 コレステロールから生成されるのはどれか。
- MT71-AM33 蛋白質に糖鎖の付加が行われるのはどれか。
- MT71-AM34 血漿中でアルブミンと結合しているのはどれか。
- MT71-AM35 血清クレアチニンが低下するのはどれか。
- MT71-AM36 血清量 0.05mL、 試薬量3.1mL、 光路長 1.0cm の条件でLD 活性を測定したところ、1分間当たりの吸光度変化量が0.020 であった。NADH のモル吸光係数を6.3×103 L・mol-1・cm-1とすると、 活性値 (U/L) はどれか。
MT71-AM29 無機質の動態で誤っているのはどれか。
- 腎不全により高マグネシウム血症をきたす。
- 副甲状腺機能低下症により高無機リン血症をきたす。
- 代謝性アルカローシスにより高カリウム血症をきたす。
- 異所性PTH 産生腫瘍により高カルシウム血症をきたす。
- 原発性アルドステロン症により高ナトリウム血症をきたす。
このような問題で最も大切なのは、「なぜその状態になるのか」をきちんと理解することです。
それぞれ選択肢を見ていきます。
1. 腎不全により高マグネシウム血症をきたす。〇正しい
正常な腎機能とは
Na・Caを再吸収 =血中Na↑Ca↑
K・P・Mgを排泄 =血中K↓P↓Mg↓
腎機能が悪くなるとこれらの機能が悪くなります
よって、Na↓、Ca↓、K↑、P↑、Mg↑ となります。
2. 副甲状腺機能低下症により高無機リン血症をきたす。〇正しい
副甲状腺はパラトルモン(PTH)というホルモンによってCaをコントロールしており、
パラトルモンにはCaの再吸収促進=血中Ca↑、リンの排泄促進作用=血中P↓があります
この機能が低下するため、血中Ca低下、血中リン増加となるわけです
3 代謝性アルカローシスにより高カリウム血症をきたす。×低カリウム血症
代謝性アルカローシスでは血中の酸(H+)が低下します。それを補うため、細胞内のH+が細胞外に出ていくと、代わりにK+が細胞内に流入します。その結果、低カリウム血症を引き起こすとされます。
参考文献:https://jsn.or.jp/journal/document/50_2/084-090.pdf
4. 異所性PTH 産生腫瘍により高カルシウム血症をきたす。〇正しい
異所性PTH産生腫瘍では、副甲状腺以外でPTHを産生する腫瘍ができてしまい、結果高Caを引き起こします。
5. 原発性アルドステロン症により高ナトリウム血症をきたす。〇正しい
アルドステロンは副腎皮質ホルモンの1つであり、Naの再吸収、Kの排泄作用があります。
すなわち、原発性アルドステロン症で過剰になると高Naとなります。
MT71-AM30 蛋白で誤っているのはどれか。
1. セルロプラスミンは銅を運搬する。
2.フェリチンは肝臓に多く分布している。
3. トランスサイレチンはビタミンAの代謝に関与する。
4. レチノール結合蛋白の血中半減期は約12時間である。
5. トランスフェリンは1分子に約 3,000 個の鉄原子を含有する。
タンパク質の特徴を覚えるべき問題で、基本事項を押さえる必要があります。
1. セルロプラスミンは銅を運搬する。〇正しい
体内の金属イオンはタンパク質と結合しているものも多く、血中の銅は95%がセルロプラスミンと結合しています。
ちなみにカルシウムはアルブミン、鉄はトランスフェリンです。このように関連の周辺知識もすぐに引き出せることが非常に大切です。
2.フェリチンは肝臓に多く分布している。〇正しい
フェリチンは貯蔵鉄とも呼ばれ、肝臓に最も多くほかに脾・骨髄などにも含まれています。
3. トランスサイレチンはビタミンAの代謝に関与する。〇正しい
トランスサイレチンは transports thyroxine and retinol(サイロキシンとレチノールを運ぶもの)からきています。すなわち、甲状腺ホルモンとビタミンAの運搬の役割があり、代謝にも関与しているといえます。
4. レチノール結合蛋白の血中半減期は約12時間である。〇正しい
レチノール結合蛋白は名前の通り、レチノールと結合する蛋白です。半減期の短い栄養タンパク(RTP:rapid turnover protein)でありトランスサイレチン(半減期2日)も該当します。
5. トランスフェリンは1分子に約 3,000 個2個の鉄原子を含有する。
トランスフェリンは鉄の運搬蛋白であり、1分子で2個の鉄(Fe)を運搬できます
鉄原子約3000個を含むのは、フェリチンのことです。フェリチンは貯蔵鉄とも呼ばれ、2の選択肢の通り、特に肝臓に多く含まれています。
MT71-AM31 ホルモンで正しいのはどれか。
1. TSH は Basedow 病で高値を示す。
2. ACTH は Cushing病で低値を示す。
3. C-ペプチドはインスリノーマで低値を示す。
4. ガストリンは Zollinger Ellison 症候群で高値を示す。
5. ADHは抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH〉で低値を示す。
一つ一つのホルモンと病気の関係性をしっかり理解すべき問題であり、非常に国試勉強のためになる問題です。
長くなりますが、丁寧に解説していきます。
1.TSH(甲状腺刺激ホルモン)は脳下垂体前葉から分泌され、このTSHが甲状腺の受容体に結合することで甲状腺ホルモンが分泌されるようになります(スイッチをONにするようなイメージ)。
そして、Basedow病は甲状腺のTSH受容体に対する自己抗体ができてしまう病気です(抗TSH受容体抗体のせいで、常にスイッチをONにして甲状腺ホルモンが過剰になってしまう)
Basedow病では甲状腺ホルモンが過剰ですから、TSHはこれ以上必要ないのでTSHの分泌が低下するということになります。
2.ACTH(副腎皮質刺激ホルモン)は脳下垂体前葉から分泌され、ACTHが副腎皮質(の受容体)に作用して、コルチゾールが分泌されるようになります。
そして、Cushing病は脳下垂体の腫瘍によって、ACTHの分泌が止まらず、結果的にコルチゾールが過剰になってしまう病気です。
すなわち、Cushing病では下垂体腫瘍によりACTHが過剰産生され高値となります。
3. Cペプチドは、インスリンの前駆体である、プロインスリンが酵素で切断された際に生じる生成物であり、生理活性はありません。
インスリノーマとは、インスリンを産生する腫瘍のことで、プロインスリンの状態で過剰産生し、そこからインスリンが過剰となってしまいます。プロインスリンが過剰になるため、そこから産生されるインスリンおよびCペプチドも高値を示します。
4.ガストリンは胃のホルモンであり、食べ物が胃に入ると胃酸などの分泌促進のため分泌されます。Zollinger Ellison 症候群はガストリノーマとも呼ばれる、ガストリンの産生腫瘍の病気です。すなわち、ガストリンが高値となります。
5.ADHは抗利尿ホルモンであり、バゾプレッシンとも呼ばれる下垂体後葉ホルモンです。
抗利尿ホルモン不適合分泌症候群〈SIADH〉とは原因は様々ですが、ADHを過剰分泌してしまう病気と思ってよいでしょう。「不適合分泌」という名前から分泌できないと勘違いしてしまうこともあるので注意しましょう。ということで、SIADHではADHは高値となります。
以上のことから正解は4になります。
各ホルモンの病態を理解することがとても大切なので、この問題の選択肢の解説を何度も納得いくまで読んでみてくださいね。
MT71-AM32 コレステロールから生成されるのはどれか。
1. 黄体ホルモン
2. 成長ホルモン
3. 副甲状腺ホルモン
4. 卵胞刺激ホルモン
5. ヒト絨毛性ゴナドトロピン
コレステロールから生成される主な生体物質は以下の3つです
・胆汁酸
・ビタミンD
・ステロイドホルモン
この問題の選択肢にあるのはすべてホルモンですので、ステロイドホルモンを選ぶ、という問題になります。
そして、ステロイドホルモンの覚え方は名前に〇〇オール、〇〇ステロン、〇〇ゲンがついているもの、なんですが選択肢はすべて日本語で書かれており、少し難しくなっています。
正解は、1.黄体ホルモン 別名をプロゲステロンといいます。この別名を知っていないと少し厳しい問題だったかもしれません。
MT71-AM33 蛋白質に糖鎖の付加が行われるのはどれか。
1. 核
2. 細胞膜
3. ゴルジ装置
4. リソソーム
5. リボソーム
これは細胞内オルガネラの基本役割を理解できているかどうか、という問題です。
糖鎖の負荷は別名グリコシル化(glycosylation)とも言います。その役割を行っているのはゴルジ装置(ゴルジ体)になります。
他の選択肢もしっかり覚えておくようにしましょう
1. 核 ー DNAの複製、遺伝子の保存
2. 細胞膜 ー 受容体を介してのシグナル伝達、トランスポーターを介した選択的透過性
4. リソソーム ー 加水分解
5. リボソーム ー 蛋白質の合成、翻訳
MT71-AM34 血漿中でアルブミンと結合しているのはどれか。
1. ケトン体
2. リン脂質
3. 遊離脂肪酸
4. コレステロール
5. トリグリセライド
アルブミンの重要な役割のひとつに「運搬」があります。
アルブミンが運ぶ主要な物質を以下に示すので必ず覚えておきましょう!
・カルシウム
・ビリルビン
・遊離脂肪酸
この3つは非常に大事です
他には、マグネシウム、甲状腺ホルモンの一部、薬物、などを運搬しています。
選択肢はすべて脂質に関するもので、脂質の中では遊離脂肪酸はアルブミンによって運ばれ、中性脂肪、リン脂質、コレステロールなどはリポ蛋白という形で存在しています。
MT71-AM35 血清クレアチニンが低下するのはどれか。
1. 脱水
2. 妊娠
3. 腎不全
4. 先端巨大症
5. うっ血性心不全
クレアチニンは通常、再吸収されず排泄される物質であり、
腎機能が低下したり、心不全で血液の流れが悪くなると、排泄が滞り血中に増加します。
ではクレアチニンが低下する場合はというと、一般的には尿量の増加を考えるとよいでしょう。
すなわち、尿崩症や妊娠時となります。妊娠時は排尿が増えるため、クレアチニンもその分排泄されて血中Creは低下します。
MT71-AM36 血清量 0.05mL、 試薬量3.1mL、 光路長 1.0cm の条件でLD 活性を測定したところ、1分間当たりの吸光度変化量が0.020 であった。NADH のモル吸光係数を6.3×103 L・mol-1・cm-1とすると、 活性値 (U/L) はどれか。
吸光度の計算問題で、ランバートベールの法則を用いるであろうことは想像がつきますが、最終的に求めるのが活性値(U/L)となっています。
ここではとりあえず、A=ε・c・l に当てはめると
0.020=6.3×103×c×1
c=0.02/6.3×103
となり、いったん計算をせずに置いておきます
血清0.05mLのところに試薬3.15mLが加わったところから、血清は3.15/0.05で63倍に希釈されています。そのため希釈前の濃度として計算すると、
c=63×0.02/6.3×103
=0.0002 mol/L となります。
次に活性値(U/L)を考えていきます。
1Uとは、1分で1マイクロモル (µmol) の基質を変化させることができる酵素量と定義されます。
そこで先ほど求めた、cの単位をµmolに変換すると
0.0002mol=0.2mmol=200µmol
ということで、答えは4となります。
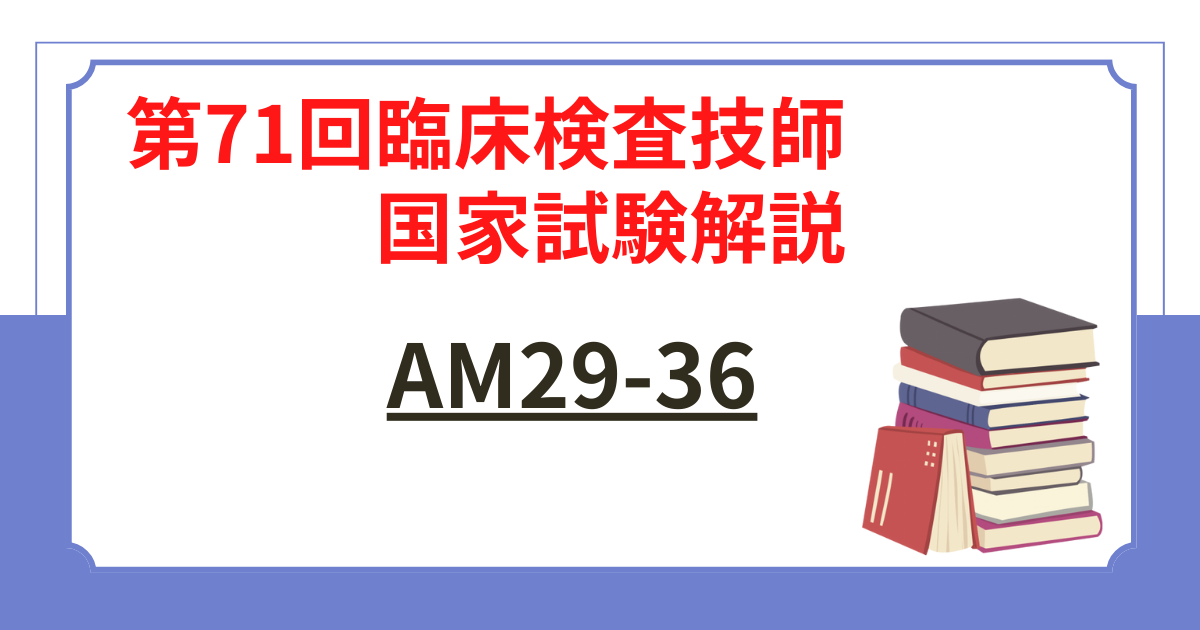
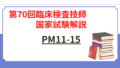

コメント