医療系国家試験の解説サイト
国試かけこみ寺です!
令和7年2月19日(水)に実施された
第71回臨床検査技師国家試験問題について
一部の分野をわかりやすく解説しています!
問題(+別冊)と解答は厚生労働省のHPで公開されています
※以下の問題の出典は全て、厚生労働省のホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-07.html)
で公開している問題を引用しています。
問題に対する解説は国試かけこみ寺のオリジナルとなります。
MT71-AM37 肝細胞癌に対して特異性が高いのはどれか。 2つ選べ。
1. AFP
2. CA15-3
3. PIVKA-II
4. PSA
5. SLX
腫瘍マーカーの問題はサービス問題といえるレベルですから、必ず覚えるようにしましょう。
特に、肝臓がんに対して特異性の高いAFP・PIVKA-II
前立腺癌に対して特異性の高いPSAは確実に覚えておきましょう。
他の重要な腫瘍マーカーについては以下の記事をご参照ください!
MT71-AM38 血漿カルシウムで正しいのはどれか。 2つ選べ。
1. イオン型は電極法で測定する。
2 アルカレミアではイオン型が上昇する。
3. 生理活性として作用するのはイオン型である。
4 総カルシウム量の30%がイオン型として存在する。
5 蛋白結合型の多くは α-グロブリンと結合している。
カルシウムの蛋白結合型とイオン型についての基礎的な問題です。
1. イオン型は電極法で測定する。→正しい。酵素法やキレート法などは血中の全Caを測りますが、イオン型のみを測定したい場合は電極法で測定することができます。
2 アルカレミアではイオン型が上昇する。→✕
アルカレミアは血液がアルカリ性に傾いている状態のことです。アルカレミアではイオン型低下、蛋白結合型が増加します。これはpHによって蛋白(アルブミン)の荷電が変化するためです。
逆に酸性の場合をアシデミアといい、イオン型増加、蛋白結合型低下となります。
3. 生理活性として作用するのはイオン型である。→正しい。血液凝固や、心筋、骨格筋の神経伝達などではCa2+が必須です
4 総カルシウム量の30%がイオン型として存在する。✕→イオン型は50%、蛋白結合型が45%、残りは化合物の状態で存在しています。
5 蛋白結合型の多くは α-グロブリンと結合している。✕→蛋白結合型は主にアルブミンと結合しています。このことから、低アルブミン血症では、カルシウムが見かけ上低値となるため補整が必要となります。
MT71-AM39 血清アルブミンで正しいのはどれか。
1. 劇症肝炎で上昇する。
2. 半減期は約7日である。
3. 座位よりも臥位での採血で低い。
4. 総カルシウム濃度と負の相関がある。
5.健常人では1日1g程度が尿中に排出される。
アルブミンの基本問題です。71回の国家試験は基礎知識を問う問題が多く、基本の重要性を再確認させられますね。
1. 劇症肝炎で上昇する。✕→低下。これが間違っていることはすぐ判断がつくと思いますが、改めてアルブミンの減少する病態について確認しておきましょう。
アルブミンが減少する原因で知っておきたいのは以下の4つです
・肝臓での合成低下:劇症肝炎、肝硬変など
・腎臓からの流出:ネフローゼ症候群、腎不全など
・炎症による消費:感染症など
・栄養不良
これを知っておくと、解ける問題の幅も多くなります
2. 半減期は約7日である。✕→半減期は約20日(3週間)です。これは栄養蛋白の中では長期の指標になります。
短期の栄養指標蛋白として
・トランスフェリン 7日
・トランスサイレチン 2日
・レチノール結合蛋白 半日
は絶対に覚えておきましょう!
3. 座位よりも臥位での採血で低い。→正しい。アルブミンは寝ている状態(臥位)の採血では座位よりも低くなります。理由として、座位や立位では水分が血管外へ移動し、臥位よりも血液が濃縮されるためです。他に、体位の影響を受ける項目として、総蛋白、赤血球などがあります。
4. 総カルシウム濃度と負の相関がある。✕→アルブミンとCaには正の相関があります、これはCaの50%がアルブミンと結合しているためです。そのためアルブミンが増加すれば見かけ上のCaも増加し、アルブミンが減少すれば見かけ上のCaも低下します。
5.健常人では1日1g程度が尿中に排出される。✕→健常人でも微量のタンパク質が尿中に排泄されますが、150mg未満です。ちなみにネフローゼ症候群の基準は尿蛋白3.5g/日です。
MT71-AM40 酵素のKm 値が10mmol/Lの場合、 最大反応速度の95%で反応させるための基質濃度 (mmol/L) はどれか。
ただし、酵素反応速度は Michaelis-Menten の式に従うものとする。
1. 70
2. 95
3. 110
4. 145
5. 190
この問題は Michaelis-Menten の式が示されていないため、まずは式を覚えていないと解くことができません。
v=Vmax・S / Km+S
まずは最大反応速度の95%と、文章にあるので、vを0.95Vmaxとして代入します
0.95Vmax=Vmax・S / Km+S まず両辺に分母を掛けて整理し、
0.95Vmax(Km+S)=Vmax・S 両辺にVmaxが出てくるので消せます、カッコ内を展開し
0.95Km+0.95S=S
0.95Km=S-0.95S=0.05S
S=19Km
Km 値が10mmol/Lの場合なので、Kmに10を代入し、190となります。
MT71-AM41 ビタミンと欠乏症の組合せで正しいのはどれか。
1. ビタミンA ー 新生児メレナ
2. ビタミンC ー 夜盲症
3. ビタミンD ー 巨赤芽球性貧血
4. ビタミンE ー 新生児溶血性貧血
5. ビタミンK ー 脚気
ビタミンと欠乏症はボーナス問題ですので、絶対に間違えられません。
まだ覚えられていない人は必ず覚えること!
1. ビタミンA 夜盲症、眼球乾燥症など
2. ビタミンC 壊血病
3. ビタミンD くる病
4. ビタミンE (新生児)溶血性貧血
5. ビタミンK 新生児メレナ
脚気はビタミンB1、巨赤芽球性貧血 (悪性貧血を含む)はビタミンB12、葉酸欠乏症にペラグラ、などがあります
MT71-AM42 脂肪細胞から分泌されるのはどれか。2つ選べ。
1. レプチン
2. インスリン
3. ガストリン
4. インクレチン
5. アディポネクチン
脂肪細胞から分泌される生理活性物質の総称をアディポサイトカインといいます。アディポサイトカインには有用なものと、そうでないものがあります。
有用なものとして、レプチン・アディポネクチンがあり、これらは動脈硬化予防的に働きます。
逆に動脈硬化を促進してしまう悪い物質として、TNF-α、PAI-1、などがあります。
MT71-AM43 経口ブドウ糖負荷試験で正しいのはどれか。
1. 検体は血清を用いる。
2. 妊娠糖尿病の診断に用いられる。
3. 試験 2時間前まで飲食が可能である。
4. 糖尿病と診断された患者に実施する。
5. 病型診断に負荷後1時間値が用いられる。
耐糖能を調べる検査である経口ブドウ糖負荷試験は、規定量(75 or 50g)のグルコース飲料を接種し、30分、1時間、2時間後に採血を行い血糖値を測定します。糖尿病型診断の基準としては2時間値が200mg/dL以上です。この検査のみでは糖尿病の確定診断はできません。
1. 検体は血清を用いる。✕→ HbA1cを測定するためEDTA・NaF管を用いた血漿での測定が一般的です。
2. 妊娠糖尿病の診断に用いられる。→正しい。妊娠糖尿病とは、妊娠時に糖尿病と診断された場合をいいます。妊娠時にインスリン抵抗性が増し糖尿病症状が現れることがあります。
3. 試験 2時間前まで飲食が可能である。✕→9~10時間前から絶食する必要があります
4. 糖尿病と診断された患者に実施する。✕→既に糖尿病と診断されている患者に行う意味はありませんし、命に危機が及ぶ可能性もあるため禁忌です。
5. 病型診断に負荷後1時間値が用いられる。→負荷後2時間値です
MT71-AM44 短期の栄養指標として用いられる血漿蛋白はどれか。2つ選べ。
1. アルブミン
2.ハプトグロビン
3. セルロプラスミン
4. トランスフェリン
5 レチノール結合蛋白
短期の栄養指標蛋白は別名RTP(Rapid Turnover Protein)とも言います。
トランスフェリン 7日
トランスサイレチン 2日
レチノール結合蛋白 半日
の3つを指します。半減期もしっかり覚えておきましょう!
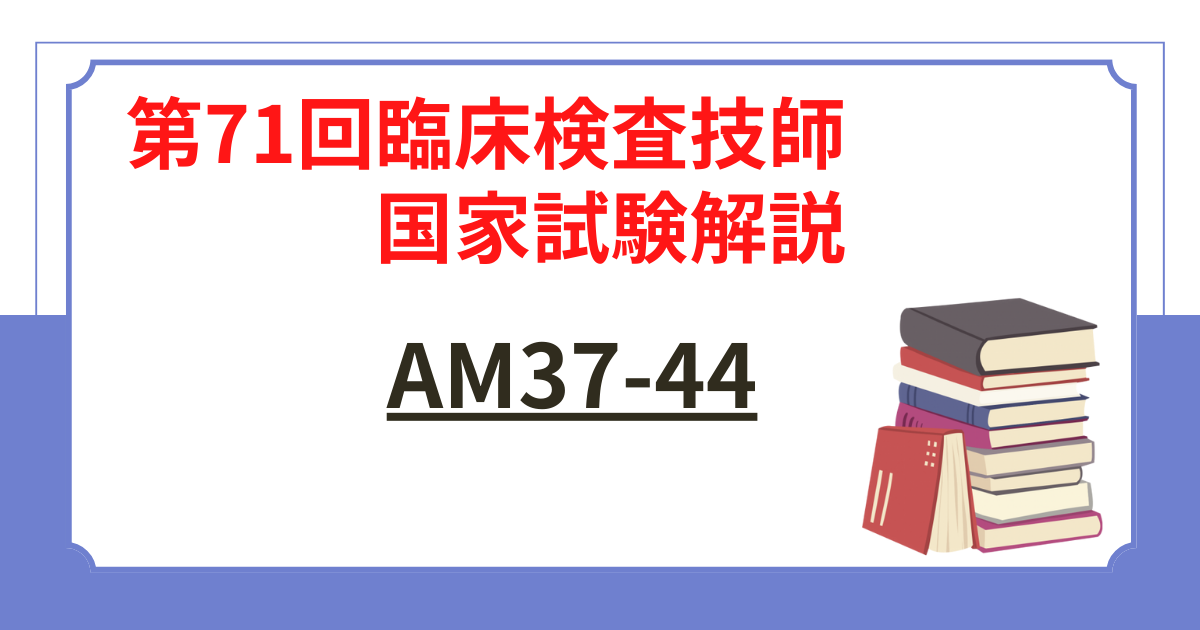
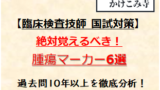
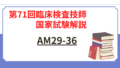
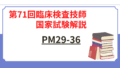
コメント