医療系国家試験の解説サイト
国試かけこみ寺です!
平成31年2月20日(水)に実施された
第65回臨床検査技師国家試験問題について
一部の分野をわかりやすく解説していきます!
問題(+別冊)と解答は厚生労働省のHPで公開されています
※以下の問題の出典は全て、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp190415-07.html)で公開している問題を引用しています。
問題に対する解説は国試かけこみ寺のオリジナルとなります。
MT65-PM8 蛋白漏出性胃腸症の診断に有用な糞便検査はどれか。
1.pH
2.ヘモグロビン
3.カルプロテクチン
4.トランスフェリン
5.α1-アンチトリプシン
・蛋白漏出性胃腸症とは
血漿タンパク(主にアルブミン)が胃腸粘膜から胃腸管腔内に異常に漏出することによって起きる低タンパク血症を主徴とする症候群です
糞便検査を行う理由は、腸管内に漏れた血漿タンパク質を検出するためです
この検査に適するのは5.α1-アンチトリプシンです
1.便のpHは通常アルカリ性ですが特定の診断にはほとんど用いません
2と4は鉄に関するもので、これらは大腸癌検診など
腸管出血を調べることに適しています
3.カルプロテクチンは好中球の放出するタンパク質で
腸管炎症によって糞便中に増加します
このことから炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)の検査に用いられます
余談:このような問題は基本は、知っていなければどうしようもない問題です。例えば、この問題はまず1を否定、2、4は便潜血検査に用いられそう…ということで3,5の二択まで絞れたとしましょう。二択まで絞れたならば、よりメジャーな方を選ぶのが無難です。α1-アンチトリプシンはタンパク血清分画でよく見かけるメジャーなものです。二択を迫られた時に、より難しい聞き慣れない言葉が正解と思いがちですが、正攻法では自分の中で聞き慣れたほうを選ぶのが無難かと思います。※あくまで個人の感想であり、考え方の一つであることをご了承ください。
MT65-PM11 高尿酸血症について正しいのはどれか。
1.偽痛風と関連する。
2.尿管結石の原因となる。
3.男性に比べて女性に多い。
4.診断基準は 9mg/dL 以上である。
5.尿酸排泄低下型に比べて尿酸産生過剰型が多い。
プリン塩基の代謝物である尿酸が、血中濃度7.0mg/dLを越えてくると飽和して結晶化します。尿酸結晶が関節にたまり、激痛を及ぼす症状を痛風発作といいます。
各選択肢を見ていきます
1.偽痛風と関連する。
偽痛風はピロリン酸カルシウム結晶が関節に溜まり、痛風のような症状を起こします
痛風に似ていますが、直接の関係はありません
2.尿管結石の原因となる。○
痛風では尿酸結晶は関節に溜まるわけですが、
尿にも大量の尿酸が排出され結石を作りやすいというわけです
正解は2です
3.男性に比べて女性男性に多い。
これは一般常識になりつつありますが男性に多いですね
女性ではエストロゲンの影響で尿酸排泄能が高いと言われています
4.診断基準は 9 7mg/dL 以上である。
5.尿酸排泄低下型に比べて尿酸産生過剰型が多い。
尿酸が増える理由として、
・尿酸産生の増加
・尿酸排出の低下
があるわけですが、尿酸排出の低下型の方が患者が多いです
MT65-PM12 急性心筋梗塞の診断に用いられないのはどれか。
1.CK-MB
2.ミオグロビン
3.心筋トロポニン T (cTnT)
4.心臓型脂肪酸結合蛋白 (H-FABP)
5.脳性ナトリウム利尿ペプチド (BNP)
正解は5になります
1~4は急性心筋梗塞のマーカーとして用いられています
ミオグロビン → H-FABP → トロポニン → CK-MB
の順番で上昇するので覚えておきましょう
(※ ただしミオグロビンは心筋特異性は低い)
脳性ナトリウム利尿ペプチド (BNP)は
慢性心不全の評価に適しています
(急性心筋梗塞でもBNPの上昇はします)
また、BNPの前駆物質であるNT-proBNPも
BNPと同様に用いられます
MT65-PM13 疾患と検査所見の組合せで正しいのはどれか。
1.腎性貧血 ー赤血球浸透圧抵抗性減弱
2.サラセミア ー直接 Coombs 試験陽性
3.遺伝性球状赤血球症 ーHbF 高値
4.自己免疫性溶血性貧血 ー血清エリスロポエチン低下
5.発作性夜間ヘモグロビン尿症 ー末梢血球細胞表面 CD55 欠損
様々な病態を理解する必要のある問題で、難易度は高めですね
こういった問題は、選択肢をひとつひとつ調べていくことで多くの知識が得られるため、まとめる価値の高い問題と言えます
1.腎性貧血 ー赤血球浸透圧抵抗性減弱血清エリスロポエチン低下
2.サラセミア ー直接 Coombs 試験陽性HbF 高値
3.遺伝性球状赤血球症 ーHbF 高値赤血球浸透圧抵抗性減弱
4.自己免疫性溶血性貧血 ー血清エリスロポエチン低下直接 Coombs 試験陽性
5.発作性夜間ヘモグロビン尿症 ー末梢血球細胞表面 CD55 欠損
正解は5です
各選択肢の病態をまとめましょう
1.腎性貧血は、エリスロポエチンの低下で引き起こされる貧血です
エリスロポエチンは腎臓で産生される造血因子です
腎臓は全身の血流量に最も敏感な臓器です。そのため、血液量が減ったりすると赤血球を増産させるためエリスロポエチンを分泌するなどして、調節をしているんですね。
2.サラセミアとはヘモグロビンの構造異常による溶血性貧血です
ヘモグロビンはα鎖2つとβ鎖2つが組み合わさり、4つのパーツ(とヘム鉄)でできているタンパク質です
サラセミアは遺伝性の疾患で、このパーツのいずれかを上手く作れずに異常なヘモグロビンが増えます
HbFは本来、胎児~新生児期に見られるヘモグロビンで、成人の場合サラセミアなどで高値となります
3.遺伝性球状赤血球症は球状の赤血球が作られ、浸透圧抵抗性が減弱することによって起こる溶血性貧血です
赤血球は表面積/容積比が小さい時に浸透圧抵抗が低下し、溶血が起こりやすくなります
具体的には、球状赤血球,楕円赤血球,有口赤血球などです
赤血球の表面の膜が引き伸ばされて薄くなるイメージですね
4.自己免疫性溶血性貧血は赤血球に対する自己抗体による溶血性貧血です
直接クームス試験は、体内で赤血球に何らかの抗体が感作しているかを調べる試験です
自己免疫性溶血性貧血はまさに自己抗体が赤血球に感作し溶血が起こるので
直接クームス陽性となります
間接クームス試験は、患者の血清側に含まれている抗体を検出する方法です
5.発作性夜間ヘモグロビン尿症は
・赤血球表面のCD55,CD59の欠損により
・赤血球の補体感受性が亢進
して、溶血性貧血となります
↓詳しくはこちらの記事で解説を行っています!
MT65-PM15 自己免疫疾患でないのはどれか。
1.悪性貧血
2.皮膚筋炎
3.重症筋無力症
4.慢性肉芽腫症
5.慢性甲状腺炎(橋本病)
こちらも各病気についての知識をまとめましょう!
正解からいうと4です
1.悪性貧血
悪性貧血は胃の内因子減少によって、ビタミンB12欠乏症が起こり
結果的に巨赤芽球性貧血を引き起こします
この原因となるのが、胃の内因子に対する自己抗体です
2.皮膚筋炎(DM)
皮膚筋炎は複数の自己抗体が原因となっていますが
抗MDA抗体が特異的であり、間質性肺炎の併発が多いです
類似疾患に多発性筋炎(PM)があり、PM/DM共通の自己抗体として
抗Jo-1抗体などがあります
3.重症筋無力症
重症筋無力症は重度の筋力低下となる病気ですが
その原因のほとんどは、アセチルコリン受容体に対する自己抗体
抗アセチルコリン受容体(レセプター)抗体です
アセチルコリンとは神経伝達物質であり、筋接合部でシグナルを伝え、筋肉を動かすことができます。重症筋無力症では自己抗体で受容体が塞がれてしまい、神経伝達が上手く行かず重度の筋力低下が起こります。ちなみに、アセチルコリンは副交感神経の神経伝達物質でもあります。
4.慢性肉芽腫症
慢性肉芽腫症は遺伝性の遺伝子異常症で(自己免疫性ではありません)
その原因はNADPHオキシダーゼという酵素の活性低下で起こる
活性酸素による殺菌機能の低下です
結果的に全身性の肉芽腫を形成する病態となります
5.慢性甲状腺炎(橋本病)
橋本病は甲状腺機能低下症です
バセドウ病とセットで覚えておきましょう
どちらも自己免疫性疾患であり
橋本病では抗サイログロブリン抗体陽性
(ただし、バセドウ病もサイログロブリン抗体陽性はある)
サイログロブリンは甲状腺ホルモンの合成と運搬に重要な役割を果たすタンパク質です。
バセドウ病では抗TSH受容体抗体陽性が見られます
TSHとは甲状腺刺激ホルモンのことです。甲状腺刺激ホルモンは下垂体前葉から分泌され、甲状腺のTSH受容体(レセプター)に結合すると、甲状腺ホルモンの分泌が促進します。抗TSH受容体抗体は、受容体のスイッチを常にONにしているようなものなので、甲状腺ホルモンの分泌が過剰となり、バセドウ病を引き起こすこととなります
臨床医学総論分野は病気の特徴・状態を説明できることが非常に重要です
そのためしっかり調べてまとめる価値のある問題が多いですね!
自分で調べるのも大変なので、国試かけこみ寺の記事を読み込んだり
記事を見ながら改めてまとめるのもよいかと思います!
ここまで読んで頂きありがとうございます!
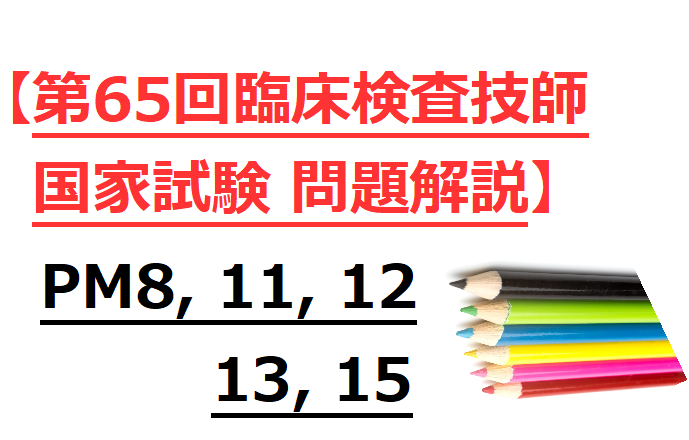
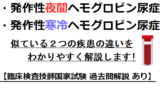

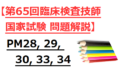
コメント