アシドーシス・アルカローシスの酸塩基平衡は
苦手な人は苦手な分野でしょうか(著者もそうでした)
苦手だから、教科書を開く気にもなりませんし
捨てちゃってもいいかな…と考えてしまったりもします
しかし!
簡単に苦手な分野を捨てるのは得策ではありません
とにかく国試の問題を解いてみましょう
重要なことは、国家試験問題の選択肢から
重要なポイントをつかみとることです
完全な理解までは至らなくとも
問題のパターンを見極めることで
点数を取れる可能性はグッと上がりますよ
それではやっていきましょう!
↓こちらの記事を読んでからだとより一層理解が深まります
酸塩基平衡の基本事項
全くの0からではさすがに問題を解いても頭に入りません
覚えるべき基本事項を書いていきます!
- 血液pHは7.35~7.45
- pHがこれを上回るとアルカローシス
- pHがこれを下回るとアシドーシス
●重要事項
PaCO2 (=血中二酸化炭素分圧 )の増減=呼吸性の変化
代謝によるHCO3– (重炭酸イオン)の変化=代謝性の変化
・アシドーシス(酸性)では PaCO2 ↑ HCO3– ↓
・アルカローシス(アルカリ性)では PaCO2 ↓ HCO3– ↑
代謝性アルカローシスについて正しいのはどれか.2つ選べ
- PCO2減少
- H+減少
- HCO3-増加
- K+増加
- Cl-増加
代謝性のアルカローシスは
体内から酸が失われるということです
pHというのはH+とOH- で定義されいますので
まず2のH+が減少すると、アルカローシスになるということがわかります
先程の重要事項として
アルカローシス(アルカリ性)では PaCO2 ↓ HCO3- ↑
を挙げています
1番の選択肢は
PCO2減少ですが、二酸化炭素は呼吸による要因が大きいため
代謝性の場合は
残りの答えは3のHCO3-増加を選ぶのが正しいです
ということで正解は2と3になります
アルカローシスの原因となるのはどれか.2つ選べ
- 下痢
- 尿毒症
- 多量の嘔吐
- 過換気症候群
- 睡眠時無呼吸症候群
この問題は形を変えて出る可能性の高い問題です
パターンを覚えましょう
各選択肢が、酸塩基どちらに傾くか
その理由を合わせて解説します
大事なのはイメージです
1.下痢
下痢をすると腸液も排泄されてしまいます
腸液はアルカリ性ですので、塩基が失われる
下痢は代謝性のアシドーシスになります
2.尿毒症
尿毒症とは腎機能低下の末期症状です
血液のpHというのは弱アルカリ性に傾いているわけですから
腎臓は 酸=H+ の排出量を調節して体内のpHを保っています
ところが腎機能低下が続くと、H+を外に出せなくなります
そのため、尿毒症も代謝性のアシドーシスとなります
3.多量の嘔吐
嘔吐すると、胃酸を外に出してしまいます
酸が外に出るので、体内は塩基性に傾く
嘔吐は代謝性のアルカローシスとなります
4.過換気症候群
いわゆる過呼吸です
呼吸性の調節は息を吐いて 炭酸ガス=CO2 を外にだすこと
つまり、過呼吸になると、体内はアルカローシス
5.睡眠時無呼吸症候群
これは過呼吸とは逆に、
呼吸が止まってしまうので、炭酸ガス =CO2 が中に溜まります
これは呼吸性のアシドーシスですね
酸塩基平衡について、正しいのはどれか2つ選べ【国試改変】
- 血液中のCO2が減少すると呼吸性アシドーシスになる
- 嘔吐により胃液を大量に失うと代謝性アシドーシスになる
- 過呼吸になると呼吸性アシドーシスになる
- 下痢でアルカリ性消化液を大量に失うと代謝性アシドーシスになる
- 腎機能の低下は代謝性アシドーシスになる
これも一つ一つ選択肢を落ち着いて考えてみましょう
1.血液中のCO2が減少すると呼吸性アシドーシスアルカローシスになる
CO2 は炭酸ガス =酸性
減少すると、体内はアルカローシスになる
2.嘔吐により胃液を大量に失うと代謝性アシドーシスアルカローシスになる
胃液は 塩酸=HCl 、酸が外に出ていくと
体内はアルカローシス
3.過呼吸になると呼吸性アシドーシスアルカローシスになる
過呼吸は CO2 炭酸ガス =酸性 を外に出しすぎる
なので、体内はアルカローシス
4.下痢でアルカリ性消化液を大量に失うと代謝性アシドーシスになる
これは丁寧に書いてくれていますね
アルカリ性消化液が外に出る
体内はアシドーシスに傾く
ということで正しいです
5.腎機能の低下は代謝性アシドーシスになる
腎臓はH+排出の調節をする
腎機能低下では、H+が中に溜まる
よって、アシドーシスになる、正しい文章!
重要ポイントのまとめ
酸塩基平衡の病態で大事なのは
- 嘔吐
- 下痢
- 過呼吸
- 腎機能低下
この4つです
それぞれアルカローシスとアシドーシスになる理由を
イメージできれば、解けるようになります
苦手分野の問題もとにかく問題を解いてみて
解説を読んで、理解しようとするところまではやってみましょう!
↓こちらの記事をもう一度読み返していきませんか?
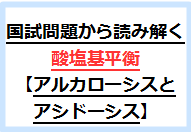
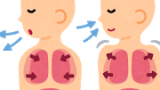
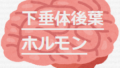
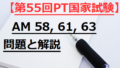
コメント