医療系国家試験の解説サイト
国試かけこみ寺です!
令和7年2月19日(水)に実施された
第71回臨床検査技師国家試験問題について
一部の分野をわかりやすく解説しています!
問題(+別冊)と解答は厚生労働省のHPで公開されています
※以下の問題の出典は全て、厚生労働省のホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-07.html)
で公開している問題を引用しています。
問題に対する解説は国試かけこみ寺のオリジナルとなります。
MT71-PM29 重炭酸イオンで正しいのはどれか。
1. 腎尿細管で再吸収されない。
2. アニオンギャップの計算式に含まれない。
3. 細胞外液中の陰イオンで最も濃度が高い。
4. 代謝性アルカローシスで血漿濃度が上昇する。
5. 動脈血中濃度 50 mmol/Lは基準範囲内である。
重炭酸イオン HCO3- についての知識を問う問題ですが、重炭酸イオン ピンポイントで聞かれることはあまりなく、やや難しめの問題と言えます。
基本知識を整理していきましょう。
まず最も大事な知識として、重炭酸イオンは体内に増加すると体がアルカリ性に傾くことを知っておきましょう。
この知識で、4が答えであることには行き着きます。
1. 腎尿細管で再吸収されない。 ✕→再吸収されます。腎臓では酸の元であるH+を排泄し、アルカリである重炭酸イオンを再吸収しpHバランスを取っています。
2. アニオンギャップの計算式に含まれない。✕→ これはアニオンギャップの式をしっかり覚えていれば大丈夫でしょう。アニオンギャップ = [Na+] – ([Cl–] + [HCO3–])
3. 細胞外液中の陰イオンで最も濃度が高い。 ✕→細胞外の陰イオンで最も多いのはクロール
4. 代謝性アルカローシスで血漿濃度が上昇する。 正しい。アルカローシス状態においては重炭酸イオンは高いことが想定されます
5. 動脈血中濃度 50 mmol/Lは基準範囲内である。 ✕→22~26 mmol/L 血ガスのデータでも重要なので重炭酸の濃度はぜひ覚えておきたいです。
MT71-PM30 日本臨床化学会〈JSCC〉 勧告法において2つ以上の酵素反応を利用しているのはどれか。2つ選べ。
1. ALP
2. AST
3. CK
4. γ-GT
5. LD
酵素の測定原理をすべて覚えるのは難しいと思いがちですが、まず知っておくべきは、2つ以上の酵素反応を利用しない、すなわち共役酵素を用いない測定方法です。
臨床検査項目における、共役酵素を用いない酵素はLD, γ-GT, ALPの3種類です
この3つ以外は測定したい酵素以外にも酵素反応を用いており、その酵素を共役酵素といいます。
この問題の答えは1,4,5を除外し、2,3が正解となります。
MT71-PM31 α-アミラーゼで正しいのはどれか。
1. エキソ型酵素である。
2. 主に肝臓で代謝される。
3. 活性中心に Zn2+を有する。
4. α-1,6-グリコシド結合に作用する。
5. 唾液腺型は膵型より分子量が大きい。
α-アミラーゼの基礎知識問題です。選択肢を一つずつ見ていきましょう
1. エキソ型酵素である。 ✕→エンド型酵素である
まずエキソ型とエンド型の違いについてですが、エンド型とは物質の構造を内部から分解する酵素、エキソ型とは物質の構造を末端から分解する酵素のことです。
α-アミラーゼはエンド型です。動物には存在しないβ-アミラーゼというのがありますがこちらはエキソ型です。
2. 主に肝臓で代謝される。 ✕→腎臓
アミラーゼを分泌するのは唾液腺と膵臓であり、唾液や膵液に分泌される他、血中にも存在します。アミラーゼは低分子であり、基本的には腎臓でろ過され尿中に排泄されます。
3. 活性中心に Zn2+を有する。 ✕→Ca2+
活性中心とは酵素を構成する分子の活性中心部分という意味で、アミラーゼの場合はCa2+を含みます。Zn2+を活性中心に含むのはALPです。また、活性化に必要なイオンとして、アミラーゼはCl–、ALPはMg2+を必要とします。
4. α-1,6-グリコシド結合に作用する。 ✕
α-アミラーゼが分解するのはα-1,4グリコシド結合です。α-1,6グリコシド結合を分解できる酵素にはグルコアミラーゼやイソアミラーゼがありますが、ヒトはこの酵素を持っていません。
5. 唾液腺型は膵型より分子量が大きい。 →正しい
正確な分子量を覚える必要はあまりありませんが、膵型アミラーゼ(P-AMY)には糖鎖がなく、唾液腺型アミラーゼ(S-AMY)には糖鎖が付加されています。糖鎖が付加されている分だけ、唾液腺の方が大きい、と覚えるとよいでしょう。
分子量 P<S であり、P型のほうが小さい分、尿に出やすいです。急性膵炎などの診断では、尿中のP-AMY測定が有用です。
MT71-PM32 サルコイドーシスの活動性マーカーはどれか。
1. プロカルシトニン
2. 心臓型脂肪酸結合蛋白
3. デオキシピリジノリン
4. アンギオテンシン変換酵素
5. N-アセチルグルコサミニダーゼ
疾患とそのマーカーは暗記必須です。
1. プロカルシトニン →敗血症 他にはプレセプシンもある
2. 心臓型脂肪酸結合蛋白 (H-FABP)→心筋梗塞 他に名前のよく似ているL-FABPがあるがこれは尿細管障害のマーカー
3. デオキシピリジノリン (DPD)→骨吸収マーカー
4. アンギオテンシン変換酵素 (ACE)→サルコイドーシス
5. N-アセチルグルコサミニダーゼ (NAG)→尿細管障害
MT71-PM33 酵素とその分類の組合せで正しいのはどれか。
1. キナーゼ ―― 異性化酵素
2. アルドラーゼ ―― 転移酵素
3. エステラーゼ ―― 脱離酵素
4. デヒドロゲナーゼ ―― 酸化還元酵素
5. トランスフェラーゼ ―― 加水分解酵素
酵素と分類については、主要なものをまず覚えましょう。
主要なものとは
・酸化還元酵素:デヒドロゲナーゼ、オキシダーゼ
・転移酵素:キナーゼ、トランスフェラーゼ
・加水分解酵素:それ以外
国家試験問題を解くうえではまず、この3つで判断を行っていくとよいでしょう。
今回の場合、答えは4とすぐわかります。
他に覚えておきたいところしては、
脱離酵素:エノラーゼ、アルドラーゼ
がありますが、これらは解糖系に登場する酵素です
MT71-PM34 分岐鎖アミノ酸はどれか。 2つ選べ。
1. バリン
2. グリシン
3. システイン
4. イソロイシン
5. トリプトファン
アミノ酸の分類は絶対に覚えましょう
分岐鎖アミノ酸は、バリン・ロイシン・イソロイシンです!
まだ覚えてない人は、下記の記事をチェック!
MT71-PM35 ビリルビンで正しいのはどれか。
1. 極大吸収波長は520nm である。
2. 2つのピロール環で構成される。
3 酸化されるとビリベルジンになる。
4. 間接ビリルビンは尿中に排泄される。
5.直接ビリルビンはHPLC法でα分画に検出される。
ビリルビンの基礎知識です
1. 極大吸収波長は520nm である。 ✕→450 nm
ビリルビンの極大吸収波長は450nmであり、ビリルビンの酸化法では450nmの減少を測定します。
2. 2つのピロール環で構成される。✕→4つのピロール環
ピロール環というのは化学構造の名前です。ヘモグロビンは4つのピロール環の中心に二価鉄を含んだものであり、鉄がないヘモグロビンの前駆物質をポルフィリンと呼びます。
3 酸化されるとビリベルジンになる。 →正しい
体内ではビリベルジンが還元されビリルビンが生成されますが、この逆反応、すなわちビリルビンが酸化されるとビリベルジンとなります。これを応用したのがビリルビン測定における酸化法です。
4. 間接ビリルビンは尿中に排泄される。 ✕→直接
間接ビリルビンは疎水性であり血液中ではアルブミンと結合し運搬されます。肝臓でグルクロン酸抱合を受け、直接ビリルビンとなると親水性となり、胆汁・便・尿などに排泄されます。
5.直接ビリルビンはHPLC法でα分画に検出される。 ✕
→HPLCではα, β, ɤ, δ に分画され、それぞれ以下のようになります
α:非抱合型ビリルビン(間接)
β:抱合型ビリルビン(1分子のグルクロン酸抱合型)
ɤ:抱合型ビリルビン(2分子のグルクロン酸抱合型)
δ:δービリルビン(抱合型ビリルビンがアルブミンと共有結合したもの)
直接ビリルビンは親水性を意味するため、α分画以外は直接ビリルビンと言えます。
MT71-PM36 ビタミンで正しいのはどれか。
1. ビタミンAは骨形成を促進する。
2. ビタミンB6はレチノールと結合する。
3. ビタミンCはコラーゲンの生成に関与する。
4. ビタミンDは血液凝固因子の生成に必要である。
5. ビタミンKはアミノトランスフェラーゼのホロ化に関与する。
これも非常に基本の基本です。
1. ビタミンDは骨形成を促進する。
肝臓で25位の水酸化、腎臓で1位の水酸化を受けて活性型となります
2. ビタミンAはレチノールと結合する。
ビタミンAはレチノール、およびレチノール関連化合物の総称です
3. ビタミンCはコラーゲンの生成に関与する。正しい
コラーゲン合成に必要なヒドロキシプロリンの生成に関与
4. ビタミンKは血液凝固因子の生成に必要である。
ビタミンK依存因子は2,9,7,10因子。他に、骨形成マーカーであるオステオカルシンの活性化にも関与します
5. ビタミンB6はアミノトランスフェラーゼのホロ化に関与する。
ASTやALTの補酵素である、ピリドキサルリン酸のことです。
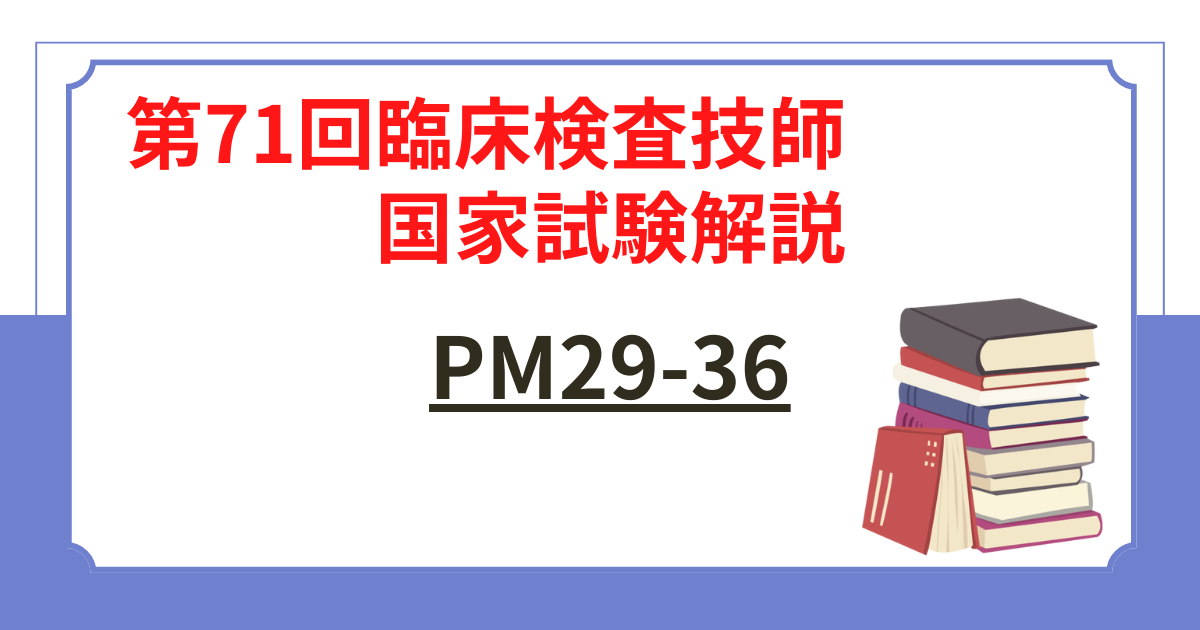
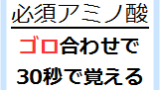


コメント